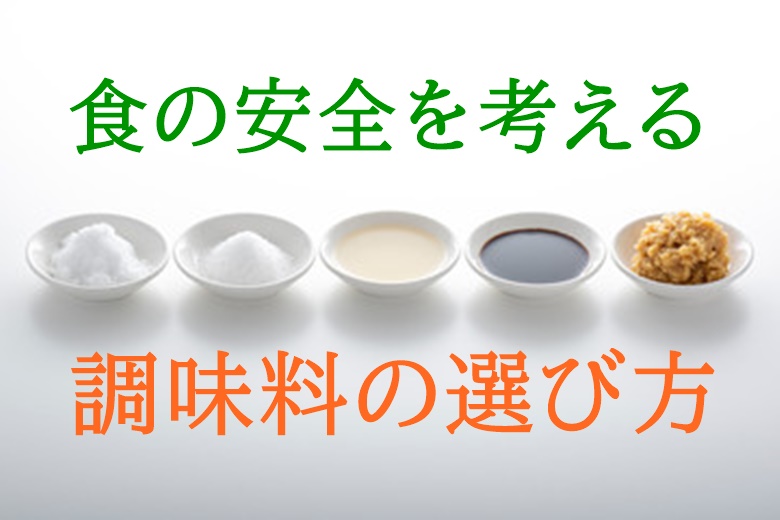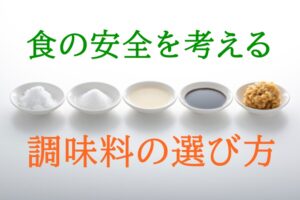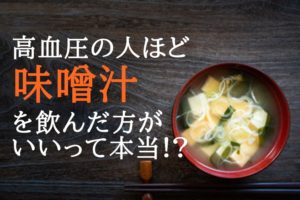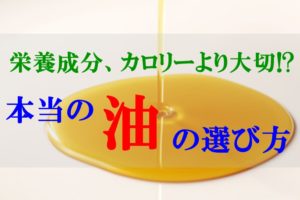- おいしくて体にいい調味料を選ぶポイント
- おすすめの無添加調味料を紹介!
あるとむ

自然食×食養生アドバイザー
食を見直してジャンクフード依存・虚弱体質から脱却。自然食品店の店長として14年の経験、食養生・薬膳などを学び得た知識を活かし、ブログやSNSで広く発信中。
2023年食養生講座をスタート、2024年初著書『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版)を出版。オンラインで食事改善の相談・サポートもしています。
健康を考えて「食」を見直すなら、まずは調味料を変えることをおすすめします。
もちろん食材も大事ですが、調味料は毎日使うものですので、ここには多少のお金をかけてでも良いものを選ぶことは必要と考えます。
ただし、いきなりすべてを品質の良いものに変えるというのは難しいですよね。

それに、どんな調味料が体にいいのかよく分からない、、、
まずは「料理のさしすせそ」に代表される日本の伝統調味料について知り、良いものを見極めてゆくのがいいです。
この記事では、「安全な食品を手に入れたい」と考えている人に、自然食品店長としての目線で砂糖、塩、お酢、醤油、そして味噌といった日本の伝統調味料の選び方を詳しく解説します。
安全でおいしい無添加調味料は、日本人が昔から大切にしてきた調味料の姿でもあります。
品質のいい調味料を選ぶことは、私たちの体だけでなく、日本の伝統を守ってゆくことにも繋がります。



品質のいい調味料を選ぶと、料理がよりおいしくなります!
記事の中では、具体的におすすめの調味料も紹介します。
ぜひ参考にしてください!
▼タップして、読みたいところからどうぞ


おいしくて体にいい砂糖を選ぶポイント


- 白砂糖(上白糖、グラニュー糖)は選ばない
- 黒糖、きび砂糖がおすすめ
- 三温糖は精製された砂糖
①白砂糖(上白糖、グラニュー糖)は選ばない
体への安全性を考えた時に、まず抑えておきたいポイントが「白砂糖を選ばない」ことです。
誤解がないようにいっておきますが、白砂糖がただ悪いというのではなく、毎日のように継続的に摂取するのはおすすめでないということです。
世の中には白砂糖が使われている製品が多くありますが、それらをすべて否定しているわけではありません。
ただし、健康を考えたときに、毎日使う調味料としては白砂糖はおすすめしません。
白砂糖については、別の記事で詳しく解説しています。
詳しく知りたい人はこちらの記事もどうぞ↓


②黒糖、きび砂糖がおすすめ
砂糖の原料は主にサトウキビと甜菜で、その搾り汁を精製し、結晶化して作られます。
白砂糖は、甘味を感じるショ糖(スクロース)以外の成分を徹底的に取り除くまで精製されています。
ちなみに、砂糖の中で最も精製度が高いのはグラニュー糖で、ショ糖の純度は99.9%。
いわば、白砂糖はビタミンやミネラルなどの成分が削ぎ落とされてしまった「ただの甘いもの」なのです。
それに対して、黒糖はサトウキビからのみ作られます。
サトウキビの搾り汁をそのまま煮詰めて、冷やして固めて作られる黒褐色の砂糖のことで、「黒砂糖」とも呼ばれます。
ショ糖の純度は80~85%で、白砂糖にはほとんど含まれていないビタミンやミネラルがたっぷりと含まれています。
苦みや渋みなど独特の風味とコクがあるのも特徴です。
かつて沖縄が長寿県といわれていた時、その理由の一つに黒糖をよく食べることが挙げられていました。
安全性と健康を考えた時、毎日の食卓には白砂糖より黒糖がおすすめです。
また、サトウキビの搾り汁から不純物を取り除いたあと、黒糖よりも多く精製し煮詰めると「きび砂糖」になります。
黒糖よりも白いですが、白砂糖ほどには精製されていませんので、多少のミネラルが残っています。
「粗糖」や「粗製糖」とも呼ばれ、かたまりになっている黒糖よりも使いやすくて人気がありますね。
③三温糖は精製された砂糖
知っておいてほしいことが、三温糖の内容です。
三温糖は、その見た目が茶色いので黒糖のように思われがちですが、実際は白砂糖に近いです。
上白糖やグラニュー糖を作るときに精製した糖蜜を、再度加熱して結晶化させたもので、焦げた糖のカラメル成分によって茶色になったものが三温糖です。



製造工程で3回温めることから、三温糖と呼ばれます。
上白糖やグラニュー糖に比べてコクや香ばしさがありますが、その内容は黒糖のようにビタミン・ミネラルが多く含まれているわけではありません。
厳選!おすすめの砂糖3つ
奄美瀬戸内純黒糖(奄美自然食本舗)
奄美大島瀬戸内町産のサトウキビのみを厳選してつくられた純黒糖です。小粒で、一口サイズの黒糖は料理だけでなく、おやつにもおすすめです。
喜界島限定きび糖(大地を守る会)
奄美諸島の一つである、喜界島で栽培されたサトウキビを使用したきび砂糖です。ミネラル分などの有機成分が、たっぷりと残っていて、料理やお菓子、シロップなどで、かたまりの黒糖よりも使いやすいです。
ビート糖(山口製糖)
北海道産てん菜(ビート)を100%原料で使用しています。サトウキビの含蜜糖に比べて、まろやかな風味でクセが少なく、あらゆる料理に幅広く使えます。黒糖ほどではないですが、ミネラルも含まれていて、見た目は白いですが、白砂糖のように血糖値を急激に上げることはありません。
おいしくて体にいい塩を選ぶポイント


- 精製塩ではなく、天然塩を選ぶ
- 岩塩より海塩の方がミネラルが多い
①精製塩ではなく、天然塩を選ぶ
塩には天然塩と精製塩、大きく分けて2種類あります。
天然塩とは本来の塩で、精製塩とは原塩を精製して作られた塩化ナトリウム99%の塩のことです。
1971年、日本は塩田を廃止し、塩は国の専売となり、イオン交換式で作られた精製塩が売られるようになりました。
海水から塩化ナトリウム(NaCl)を抽出する「イオン交換式」は塩を大量生産させるための製法で、海水に元々含まれる微量なミネラルを取り除き、塩化ナトリウムが99%という精製された状態の塩をつくります。
1997年に塩の製造が自由化されてからは、天然塩が市場にも出回るようになりましたが、大量生産されている精製塩は、現在も多くの食品に使われています。
近年は「減塩すべき」という意見が多く聞かれますが、私たち人間にとって塩はとても重要なものです。
たしかに塩の摂り過ぎは体によくないですが、塩の摂らなさすぎも体に悪いです。
その理由については、別の記事で詳しく書きましたので、ぜひ参考にしてください。


②岩塩より海塩の方がミネラルが多い
天然塩の中にも「海塩」「岩塩」「湖塩」と種類があります。
- 海塩(天日塩) 海水を太陽光で乾かして作るもの
- 岩塩 海水が地殻変動によって陸地に取り込まれ、それが蒸発して成分が結晶化したもの
- 湖塩 地殻変動によって、海水が湖に取り込まれたもの
岩塩や湖塩は外国産が多く、日本で天然塩といえば海塩を指します。
海塩は「天日塩」とも呼ばれ、塩田などを利用して、太陽の光、風など自然の力を頼りに凝縮して作られます。
海塩は海水が原料なので、海水に溶け込んでいるミネラルが多く含まれていて、重要なミネラル補給源です。



多いもので約70種類のミネラルを含む天日塩があります!
ただし、現在は「海の汚染」も深刻ですので、より安全な塩を選ぶ必要がありますね。
厳選!おすすめの塩3つ
恵安の潮(海塩隊)
中国の歴代皇帝が愛用した塩としても有名な、完全天日熟成海塩です。中国福建省の特殊な塩田で作られ、古代より広東料理、禅寺の精進料理に使われていた塩です。平釜で煮詰める工程が一切なく、太陽と風と遠赤外線のみで自然結晶させ、半年以上じっくり寝かせた特級の海塩です。ミネラルバランスは抜群で、料理にも健康にもおすすめの塩です。
土佐の塩丸(土佐の塩丸)
国産の天日塩です。満潮時の海から汲み上げた海水を、天日や風などの自然の力だけで結晶させた塩は、まろやかな旨みがあり、おにぎりに使うだけでその美味しさを味わえます。
ぬちまーす(ぬちまーす)
こちらは天日塩ではありませんが、沖縄の海水100%を原料に、世界初の「常温瞬間空中製塩法」という独自の技術で作られたミネラルの種類が豊富な塩です。特にマグネシウムを多く含み、その含有量は一般の食塩の200倍です。塩そのものの旨み、上品な味わいが老舗の日本料理店など、食のプロに認められている注目の塩です。
おいしくて体にいいお酢を選ぶポイント


- 醸造酢を選ぶ
- 静置発酵法のものを選ぶ
- 有機原料が良い
①醸造酢を選ぶ
お酢には「醸造酢」「合成酢」「加工酢」と3種類あり、昔ながらのお酢は「醸造酢」で、天然の発酵菌を利用して酢酸発酵させたものです。
醸造酢は基本的に無添加で、天然の原料を使うため製造過程に時間がかかり、その分のコストがかかります。
しかし、有機酸やアミノ酸、ビタミンなどの栄養価が非常に高く、それによる健康効果が期待されます。



お酢は昔から健康に良いものとして認識されていました!
それに対して「合成酢」は、酢酸を水で薄めてから、砂糖や酸味料、醸造酢を加えたものです。
発酵、熟成の過程がないので、短期間でつくることができますが、醸造酢のような効能はありません。
また、「加工酢」は醸造酢や合成酢に調味料を加えて味付けされたものです。
よく使われる「ポン酢」などがそうですが、食品添加物や化学調味料が多く使われているものもあります。
②静置発酵法のものを選ぶ
お酢の発酵法にも種類があり、それが「静置発酵法」と「速醸法」です。
「静置発酵法」は昔ながらの伝統製法で、発酵には3~4か月かかります。
対して、「速醸法」とは酒に空気を送り込んで2~3日で発酵させる製法です。



発酵にかけている時間が違いすぎますね、、、
速醸法は短時間で製造できるため、ローコストで大量生産が可能です。
現在市場に出回っているお酢のほとんどがこの製法だといわれています。
やはり、じっくりと時間をかけて造られる「静置発酵法」の方が、まろやかで深みのあるお酢が出来上がります。
③有機原料が良い
お酢の原料となるお米、穀物、果実の質も大切です。
どんなに良い製法でも、原料が良くなければ良いお酢はできません。
美味しさだけでなく安全性にもこだわるなら、有機原料のものをおすすめします。
お酢の製法に関しては別の記事で詳しく解説しています↓


厳選!おすすめのお酢3つ
有機純米酢(マルシマ)
有機栽培のうるち米だけを原料に、昔ながらの製法にこだわって醸造されたお酢です。お酢にはさまざまな種類がありますが、日本では純米酢が基本的なお酢で、どんな料理にも使いやすいです。
桷志田有機三年熟成(福山黒酢)
日本が誇る伝統的な黒酢です。黒酢発祥の地・鹿児島県霧島市福山町で、江戸時代から続くといわれる「かめ壺製法」により、じっくりと時間をかけて熟成されたお酢には、酢酸をはじめ、必須アミノ酸、ビタミンB群を非常に多く含んでいます。原料に使われている玄米も有機栽培で安全です。ハチミツと混ぜてドリンクにしても美味しく飲めて、夏場の熱中症予防に最適です。
有機バルサミコ酢(アルチェネロ)
イタリアの名産バルサミコ酢は、その昔、貴族に愛された健康酢です。発酵熟成に最低でも12年かかるとされ、そのフルーティーな香りとまろやかな酸味は、お肉料理や魚料理、サラダ、デザートにも使える万能なお酢です。
おいしくて体にいい醤油を選ぶポイント


- 原料が「大豆、小麦、塩」のみの醤油を選ぶ
- 原料は国産100%のものが良い
- 大豆は脱脂加工大豆ではないもの
- 塩は天然塩がいい
- 天然醸造、木桶仕込みが昔ながらの醤油
①原料が「大豆、小麦、塩」のみで、国産100%のものを選ぶ
本来、醤油は大豆、小麦、塩を原料に、ゆっくりと時間をかけて熟成してつくられます。
その平均的な製造期間は1~2年といわれ、時間をかけなければ、うまみや風味を引き出すことができないからです。
しかし、現在流通している醤油のほとんどに、食品添加物や化学調味料が使われています。
なぜ添加物が必要かというと、大量生産しているからです。
醤油に限らず、モノを大量に生産するためには、できるだけコストを下げ、時間をかけずに作る必要があります。
醤油は発酵させてから、じっくりと熟成させてつくられるものです。
だから、その足りないところを添加物を使って補っている、ということになりますね。



無添加の醤油は原材料欄を見れば分かります!
まずは「大豆、塩、小麦」のみ記載されている醤油を選びましょう。
②原料は国産100%のものが良い
その上で、原料は国産100%がおすすめです。
なぜなら輸入大豆には、遺伝子組換えやポストハーベスト農薬の問題があるからです。
この辺については、別の記事で詳しく書いていますので、ぜひ1度読んでみてください。


③大豆は脱脂加工大豆ではないもの
原料の大豆は「脱脂加工大豆」でないものを選びましょう。
脱脂加工大豆とは、大豆油を採る際に醤油醸造用にたんぱく質含量や粒度を特別に調整した専用品のことです。
大豆から油を取り除いた後の「搾りかす」のようにいわれることがあります。
油をあまり含んでいない分、うまみ成分の指標となる窒素分が多くて、またフレーク状になっていることもあり、成分の分解や溶出が速いという特徴があります。
また、通常の丸大豆に比べて安価で、しかも短時間で醤油をつくることができることから、現在国内で製造されている約80%の醤油が脱脂加工大豆を採用しています。
しかし、こだわりの醤油をつくる蔵元は脱脂加工大豆を使いません。
丸大豆と比較すると、栄養価が低く、本来の醤油の旨みが得られないからです。
④塩は天然塩がいい
大豆、小麦同様に「塩」も醤油の味を決める重要な原料です。
塩については前述した通りで、やはり天然塩がおすすめです。
塩に対してこだわりがある会社は、その塩がどんな塩かも明記しています。
⑤天然醸造、木桶仕込みが昔ながらの醤油
醤油の製法は「本醸造」「混合醸造」「混合」の3つがあります。
- 本醸造 昔ながらの製法
- 混合醸造 もろみ(醤油になる前の状態)にアミノ酸液を加える製法
- 混合 醤油を絞ったあと、アミノ酸液を入れる製法
昔ながらの醤油のつくり方は「本醸造」ですが、中には食品添加物が使われているものもあります。
そこで、安全性と健康を考えるなら「天然醸造」がおすすめです。
「天然醸造」とは、発酵を促進する酵素等を一切添加せずに、ゆっくりと時間をかけて自然に作られる醤油です。



本醸造の中でも、さらに良い醤油のつくり方が「天然醸造」!
そして、「天然醸造」は「木桶仕込み」でもあります。
昔ながらの醤油は、天然杉でつくった木桶を使って仕込んでいます。
木桶は四季の温度変化をそのまま中に伝えて、自然のままに発酵ができるという特徴があります。
木桶には菌が住みつくので、その蔵ごとの特徴を生み出します。
現在は、木桶を使う醤油屋はどんどん減っていて、木桶仕込みの醤油は全体の1%ほどといわれています。
厳選!おすすめの醤油3つ
ヤマヒサ有機醤油(ヤマヒサ)
醤油の産地として有名な香川県小豆島にある「ヤマヒサ」の有機醤油です。ヤマヒサは日本の中でも先駆けて有機原料を使った蔵元で知られています。国産の有機栽培大豆・小麦、そして天日塩を使用した杉樽仕込みの天然醸造醤油は、まさに理想的な「安全で美味しい醤油」です。
大徳醤油(大徳醤油)
兵庫県但馬地域で100年以上の歴史がある大徳醤油です。国産丸大豆、国産小麦を100%使用。そしてミネラル豊富な国産平釜塩で仕込んだ天然醸造の醤油です。国産原料にこだわり、化学調味料・保存料・着色料・エキス・遺伝子組換え原料を一切使用していない安心安全で美味しい醤油です。
井上古式醤油(井上醤油店)
無添加で、国産原料にこだわった本醸造の醤油で、多くの料理家に利用されていることで知られています。通常の醤油よりも2割多く大豆を使っていることから、とても濃厚な味になっています。
おいしくて体にいい味噌を選ぶポイント


- 無添加の味噌を選ぶ
- 国産原料100%のもの
- 可能なら手作りがいい
①無添加の味噌を選ぶ
味噌は比較的、食品添加物が使われない調味料ですが、保存料や防腐剤、中には化学調味料が使われている味噌もあります。
本来、味噌は麹菌を利用して発酵させて作っているので、商品化した後も毎日発酵が続いています。
色や香り、風味は徐々に変化して、味噌を入れてある袋が膨張することもあります。
そのため、商品の均一化を目的に、酒精などの食品添加物を使って麹菌のはたらきを抑えてある商品もあります。
しかし、麹菌のはたらきを抑えるということは、発酵が止まるということ。
つまり、その時点で発酵食品ではなくなってしまいますね。



味噌は発酵食品であるから価値があります。
時間が経てば色や香り、風味が変わってしまうことを理解して、無添加の味噌を選びましょう。
もちろん、手作りが1番おすすめです!
②国産原料100%のもの
味噌も醤油同様、大豆、小麦、塩が一般的な原料です。
輸入された農産物には、遺伝子組換えやポストハーベスト農薬の問題があります。
安全性、そして美味しさを考えるなら、国産原料100%で無添加の味噌がベストです。
近年、国内での味噌の消費が減っていると指摘されていますが、反対に海外への味噌の輸出量は増え続けているんですよね。
味噌の効能効果に世界中が注目しています。



味噌は間違いなく、日本が世界に誇る素晴らしい調味料です!
味噌の働きについては、別の記事で詳しく解説しています。
味噌の内容については、もっと多くの人に知ってもらいたいですね。
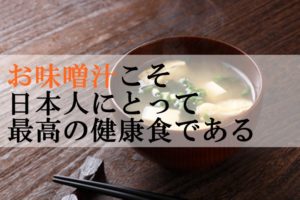
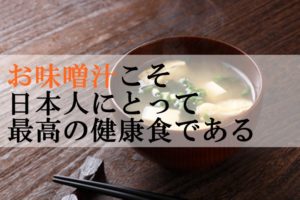
③可能なら手作りがいい
手づくりに勝るものはありません(笑)
※「マルカワみそ」さんが教える作り方が分かりやすいです→「簡単手作り味噌の作り方」
厳選!おすすめの味噌3つ
有機みそ日本(マルカワみそ)
こだわりの味噌をつくることで知られる「マルカワみそ」の代表作。安心安全な原料と製法にこだわった生味噌です。「たった一杯の味噌汁が日本の未来を変えていく」という創業の思いと熱意が込められた味噌は絶品です!ぜひ1度味わってみてほしいです。
無添加まぼろしの味噌熟成麦(山内本店)
厳選された国産大豆・大麦・塩を使用し、阿蘇の伏流水で仕込んだ無添加・中甘口の熟成麦味噌です。麦の濃厚な旨みとふくよかな甘みが際立つ香り豊かなお味噌は、お味噌汁はもちろん、野菜にそのままつけてもおいしく味わえます。
味噌手作りセット(百川味噌)
初めての人におすすめの味噌づくりキット。大豆、塩、米麹、種味噌、そして樽までついてます。自分でつくる味噌は、自分の常在菌が入るので、世界に一つだけの味噌になるんです。ぜひチャレンジしてみてください!
まとめ


健康を考えて食を見直す。
食のすべてを安全な商品で取り揃えるのは、簡単なことではありません。
その分の知識とお金が必要になります。
食生活を見直すならまずは調味料、特に「さしすせそ」といわれる日本の伝統調味料をより良いものに変えてみましょう!
調味料は毎日使うもの。
安心安全で昔ながらの調味料を使えば、食生活は今よりきっと豊かになるはずです。
安全でおいしい食品を選ぶことは、私たちの健康に良いだけではありません。
調味料でも野菜でも、食品の大量生産の裏で、少なからず環境や動物の犠牲が生まれています。
つまり、良い食品を選ぶことは環境を守ることにも繋がります。
私たちの「食」を選ぶ行為が、社会全体にも影響を与えるんですね。